コラム
熱中症対策義務化の対策例を紹介 企業が取るべき具体的措置と罰則を解説
2025年9月18日
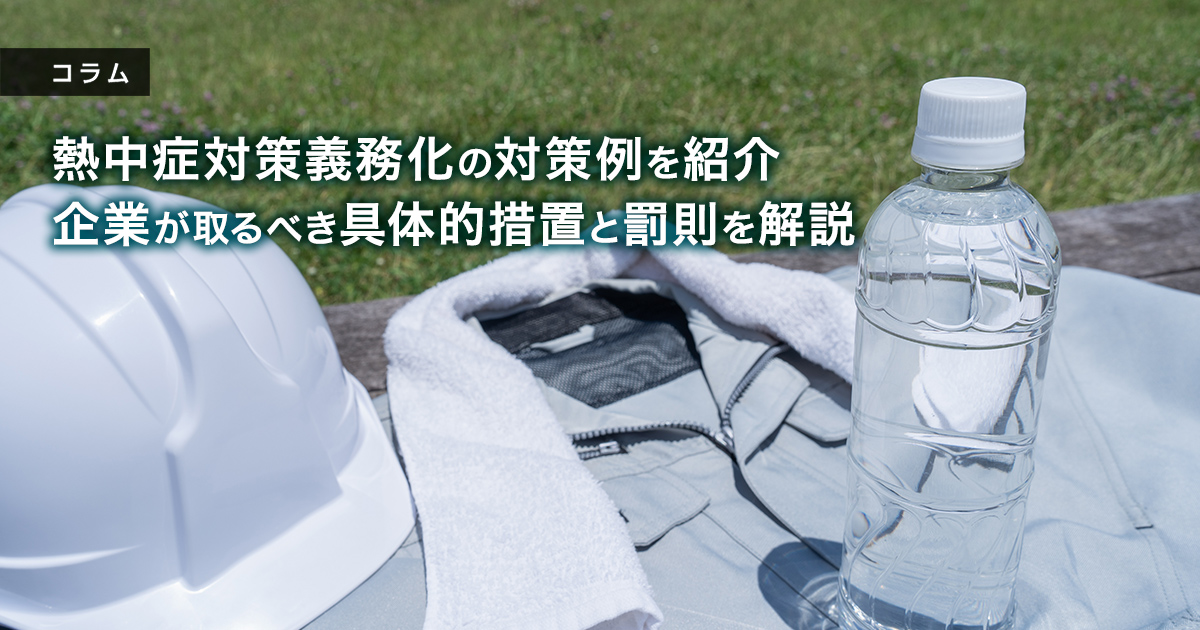
近年、夏の猛暑は厳しさを増しており、職場における熱中症のリスクは年々高まっています。このような状況を受け、労働者の安全と健康を守るため、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、事業者による熱中症対策が罰則付きで義務化されることになりました。
これまで努力義務とされてきた対策が法的な義務となり、企業にはより一層具体的な対応が求められます。本記事では、熱中症対策の義務化によって何が変わるのか、企業が具体的に何をすべきなのかを、対策例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
- 1 - 2025年6月から熱中症対策が義務化!何が変わる?
- 義務化の背景にある労働災害の現状
- 義務化の対象となる事業者と作業環境
- 違反した場合の罰則について
- 2 - 義務化で企業に求められる具体的な対策とは?
- WBGT値(暑さ指数)の把握と管理
- 熱中症発生時の対応手順の策定
- 労働者への安全衛生教育の実施
- 体調不良者への配慮と作業転換
- 3 - 【場所別】すぐに実践できる熱中症対策の具体例
- 工場・倉庫での対策例
- 建設・屋外現場での対策例
- オフィスでの対策例
- 4 - 熱中症対策に有効なアイテム・設備一覧
- 【個人装備】空調服や冷却グッズ
- 【環境改善】スポットクーラーやミストファン
- 【水分補給】経口補水液や塩分タブレット
- 5 - まとめ:計画的な準備で万全な熱中症対策を
1 - 2025年6月から熱中症対策が義務化!何が変わる?
今回の法改正は、職場での熱中症による労働災害が後を絶たない状況を踏まえたものです。まずは、義務化の背景と概要、そして違反した場合の罰則について正しく理解することが、対策の第一歩となります。
義務化の背景にある労働災害の現状
厚生労働省の発表によると、2024年の職場における熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,257人にのぼり、依然として高い水準で推移しています。特に、死亡災害に至るケースでは、発見の遅れや初期対応の不備が重篤化の要因となることが少なくありません。
こうした深刻な状況から、国は労働者の命と健康を守るためには、事業者による対策をより強化する必要があると判断し、罰則を伴う義務化へと踏み切りました。
義務化の対象となる事業者と作業環境
今回の義務化では、すべての事業者が対象となりますが、特に以下のいずれかの条件に該当する「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、具体的な措置を講じることが義務付けられます。
-
- • WBGT値(暑さ指数)が28度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業
- • 気温が31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業
建設業や製造業の屋外・屋内作業はもちろんのこと、警備業、運送業、さらには空調設備が不十分なオフィスなども対象となる可能性があります。
違反した場合の罰則について
事業者が義務付けられた措置を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。 これは、単なる行政指導にとどまらず、企業の経営に直接的な影響を与える厳しい内容です。従業員の安全を守ることはもちろん、企業のリスク管理の観点からも、確実な対応が求められます。
2 - 義務化で企業に求められる具体的な対策とは?

今回の義務化では、熱中症による重篤化を防ぐための体制整備や手順の作成、そして関係者への周知が中心的な要件となります。企業が具体的に講じるべき措置は多岐にわたりますが、特に重要なポイントを解説します。
WBGT値(暑さ指数)の把握と管理
WBGT値(暑さ指数)は、気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの熱)などを取り入れた、人体への熱ストレスを表す指標です。事業者は、作業場所のWBGT値を測定し、その値に応じた対策を講じる必要があります。
| 区分 | 身体作業強度(代謝率レベル)の例 | 暑熱順化者の WBGT基準値(℃) | 暑熱順化していない者の WBGT基準値(℃) |
|---|---|---|---|
| 0 安静 | 安静、楽な座位 | 33 | 32 |
| 1 低代謝率 | 軽い手作業(書く、タイピング等)、手及び腕の作業、脱立位の静的作業など | 30 | 29 |
| 2 中程度代謝率 | 繰り返す手及び腕の作業(くぎ打ち、打ち抜き等)、脱立位の作業、腕と脚の作業など | 28 | 26 |
| 3 高代謝率 | 強めの反復及び困難な作業(ショベル作業、ハンマー作業等)、頭上作業や手押し車を押し続ける作業など | 26 | 23 |
| 4 極高代謝率 | 最大速度の速さでのとても激しい運動、きわめて重いものを使ったり、担ったりするなど | 25 | 20 |
WBGT値が基準を超える場合は、冷房の使用、作業時間の短縮、休憩時間の増加など、作業環境の低減措置を講じなければなりません。
熱中症発生時の対応手順の策定
万が一、職場で熱中症の疑いがある従業員が出た場合に、迅速かつ適切に対応するための手順をあらかじめ作成し、全従業員に周知することが義務付けられます。具体的には、以下の内容を盛り込んだマニュアルなどを整備します。
-
- • 症状の確認方法と重症度の判断基準
- • 現場での応急処置(涼しい場所への移動、衣服を緩める、体を冷やすなど)の手順
- • 医療機関への連絡・搬送のタイミングと基準
- • 緊急連絡網(管理者、救急、病院など)の整備と掲示
労働者への安全衛生教育の実施
熱中症は、本人が自覚しにくい場合もあるため、予防には労働者自身の知識も不可欠です。事業者は、労働者に対して、熱中症の症状、予防方法、応急処置、WBGT値の意味などに関する安全衛生教育を定期的に実施する必要があります。 新規入場者や経験の浅い作業員に対しては、特に丁寧な教育が求められます。
体調不良者への配慮と作業転換
作業開始前の朝礼などで、労働者の健康状態を確認することも重要です。睡眠不足や二日酔い、発熱などの体調不良は熱中症のリスクを高めるため、申告しやすい雰囲気をつくり、該当者には無理をさせず、作業内容の変更や配置転換などの措置を講じることが求められます。
3 - 【場所別】すぐに実践できる熱中症対策の具体例

義務化された対策を確実に実行するためには、作業場所の特性に応じた具体的な工夫が効果的です。ここでは、場所別に実践できる対策例を紹介します。
工場・倉庫での対策例
高温になりがちな工場や倉庫では、環境改善が重要な鍵となります。熱源となる機械の排熱方向を工夫したり、断熱材を導入したりすることに加え、スポットクーラーや大型の工業扇を設置して、作業エリアを局所的に冷やす方法が有効です。また、こまめな換気で熱気を外部に排出し、作業員の近くに冷たい飲料水や塩分補給ができる飴などを常備することも忘れてはなりません。
建設・屋外現場での対策例
直射日光やアスファルトの照り返しが厳しい建設現場では、まず作業時間の調整が基本です。比較的涼しい早朝や夕方に作業時間をシフトさせたり、日中の最も暑い時間帯(14時~17時頃)には長めの休憩時間を設けたりするなどの工夫が求められます。また、テントやミスト発生器を設置した休憩場所を確保し、いつでも涼める環境を整えることが重要です。
オフィスでの対策例
空調が効いているオフィスでも、窓際や日当たりの良い場所、OA機器が密集しているエリアは室温が高くなりがちです。サーキュレーターで空気を循環させ、室温のムラをなくす工夫が有効です。また、クールビズを徹底し、従業員が体温調節しやすい服装で働けるように配慮することも大切です。ブラインドや遮熱フィルムを活用して、窓からの直射日光を防ぐだけでも室温の上昇を抑える効果が期待できます。
4 - 熱中症対策に有効なアイテム・設備一覧

企業の対策をサポートする様々なアイテムや設備があります。これらを組み合わせることで、より効果的に熱中症を予防することができます。
【個人装備】空調服や冷却グッズ
近年、屋外作業者を中心に急速に普及しているのが、ファン付きウェアです。衣服内に風を送ることで汗を気化させ、その気化熱で体を冷やす仕組みで、酷暑環境下での体温上昇を効果的に抑制します。このほか、水に濡らして首に巻くクールタオルや、ヘルメット内に装着する送風機なども手軽に導入できる対策として有効です。
【環境改善】スポットクーラーやミストファン
工場や屋外など、空間全体を冷やすことが難しい場所では、スポットクーラーやミスト発生器が活躍します。作業者をピンポイントで冷やしたり、微細なミストの気化熱を利用して周辺温度を下げたりすることができます。休憩場所に設置するだけでも、作業員の体力を効果的に回復させることができます。
| 設備の種類 | 特徴 | 主な活用場所 |
|---|---|---|
| スポットクーラー | 特定の場所を強力に冷却する。移動も可能。 | 工場、倉庫、イベント会場 |
| 大型扇風機 | 大風量で広範囲に風を送り、体感温度を下げる。 | 体育館、工場、屋外現場 |
| ミストファン | 水の気化熱を利用して周辺温度を下げる。粉塵抑制効果も。 | 建設現場、畜産施設、屋外イベント |
| 遮熱シート | 屋根や壁に施工し、太陽光の熱を反射して室内への侵入を防ぐ。 | 工場、倉庫、体育館 |
【水分補給】経口補水液や塩分タブレット
熱中症対策の基本は、こまめな水分・塩分補給です。汗をかくと水分だけでなく、体内の塩分(ナトリウム)も失われます。水だけを大量に飲むと、かえって体内の塩分濃度が下がり、危険な状態に陥ることもあります。スポーツドリンクや経口補水液、塩分補給用のタブレットや飴などを常備し、労働者がいつでも摂取できるようにしておくことが重要です。
5 - まとめ:計画的な準備で万全な熱中症対策を
2025年6月から始まった熱中症対策の義務化は、すべての事業者にとって重要な課題です。罰則が科されるというリスクだけでなく、従業員の命と健康を守り、安心して働ける職場環境を提供することは、企業の社会的責任であり、持続的な成長の基盤となります。
今回紹介した内容を参考に、自社の作業環境を改めて見直し、WBGT値の管理体制の構築、具体的な対策の導入、そして従業員への教育を計画的に進めてください。
編集:株式会社JVCケンウッド・公共産業システム マーケティング担当(2025年9月)
※本資料は、公開掲載時点での情報であり、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※本資料内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
<参考資料・出典>
令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します|厚生労働省
職場のあんぜんサイト:暑さ指数(WBGT値)[安全衛生キーワード]
労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索



